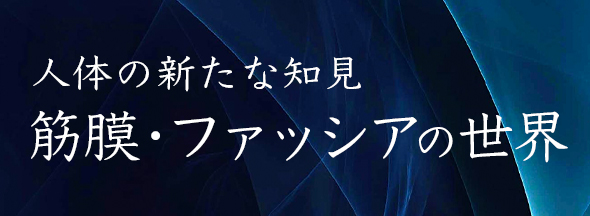鍼灸師にとってのWell-being【第3回】Well-beingは手段ではなく結果である(全3回シリーズ最終回)
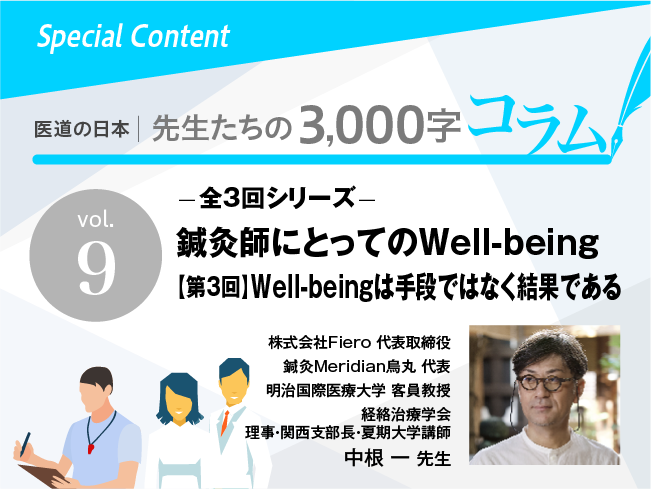
Well-beingという骨太の方針
前回のコラムでは、Well-beingが世界的ムーブメントとなりつつある背景と、日本の現状について紹介させて頂きました。 統計的にみるとGDPと幸福度は必ずしも正相関にあるとは言えず、社会が不定になるケースもあるという懸念が示されたことから、我が国でも国家プロジェクトとして取り組むこととなっています。 件の『骨太の方針2021』でどのように表明されているのか、その文言を確認してみましょう。
<経済財政運営と改革の基本方針 2021>
第3章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革
▽ EBPMの基盤であるデータ活用を加速するため、全ての基幹統計をデータベース型で原則公表するよう、データ公表様式の標準化方針を策定する。感染症等の社会経済のリアルタイムデータを迅速に収集し、分析能力を向上させ、きめ細かな政策立案につなげる。こうした取り組みの一環として、政府の各種の基本計画等について、Well-beingに関するKPIを設定する。
※EBPM(Evidence Based Policy Making)
⇒個々の政策に実質的な効果があるかどうかを可能な限り厳密に検証して、実質的な効果があるという証拠があるものを優先的に実施しようとする態度
※KPI(Key Performance Indicator)
⇒重要業績評価指標のことで、KGIを達成するための中間指標である。
※KGI(Key Goal Indicator)
⇒重要目標達成指標のことで、売上高や成約数、利益率などが該当する。
2000年を迎えるタイミングで厚労省によって提示された『健康日本21』は、私たち鍼灸師が大きく社会に貢献することができる好機かに思われましたが、食生活・運動習慣・受動喫煙・飲酒・街づくり・自治体や企業による基盤整備による健康寿命の延伸と健康格差の縮小が目的とされたので、残念ながらセンタープレイヤーにはなれず…。
翻って今回のWell-beingに関する取り組みは、国家運営の基本方針としてすべての施策が国民の主観的幸福度を勘案することを義務付けたものです。 また「幸福」という目的は「健康」を包含する壮大なテーマなのでステークホルダーの裾野が広く、私たちが寄与参画する余地が十分に見込まれます。
Well-doingではなくWell-beingを社会実装させる
日本社会が向かうべき方向が示されたことで、各業種の大手企業はこぞってWell-beingをCSRに実装すべく「健康経営」を掲げ始めました。社員の幸福度が上がれば業務効率が上がり企業は成長するはずですが、先にもお話ししたとおり主観的幸福度を上げる要件が「給料」という人もいれば「休暇」という人もあり、施策が難しいのです。
しかし「健やかであること」を幸福の要因として否定する人はいません。 いま元気な人も、何らかの病気を抱えている人も、あらゆる状況にある人が健やかに日々を過ごすことを幸せだと感じます。どれだけ価値観が多様になっても、その一点だけはみんなで同意できるのです。
そのことから健康診断を勧めて、病気の早期発見を促すことが一つの答えになっています。 既存の仕組みをアナウンスし直して運用するだけで良く、また検診を受けた人数を過去のデータと比較すればKPIは提示できるので、スピード感があります。
「ところで、健康診断を受けている人は幸福を感じているのでしょうか?」
Well-beingは読んで字の如く、行動ではなくて「在り様」のことを指しています。健康であるために健康診断を受けて、健康になるためのセルフケアを生活に取り入れることはとても良いことなのですが、これはWell-doingであってWell-beingとは少し違うことなのです。 「血糖値を下げるために運動をしろって、主治医に言われたから…」と、義務感に駆られて7000歩を歩いている時間はWellには感じられませんよね。
もちろん物事の取り組み方には個性がありますから、課題達成型の人はWell-doingをしている自分にWell-beingを感じるかもしれません。 そのような人も含めてWell-beingを標榜するからには、その動機も関わっている時間も、ワクワクしたり心が落ち着くといった前向きな心持であって欲しいと願うのです。
世界中を熱狂させた「ポケモンGo」(任天堂)というゲームは、スマートフォンに搭載されたGPSによる位置情報を利用して、歩いた距離によってミッションを達成していくというゲームです。 歩くことによる身体的効果もさることながら、精神的な健康にも貢献したというデータがPub Medに掲載されています。 楽しくゲーム参加をしていたら健康になっていたというストーリーは、まさにWell-being!!
「朝の景色を眺めるのが好きだから毎日1時間くらい散歩をしていたら、血糖値が下がっていた」という日々はきっと幸せなことでしょう。楽しさ、心地よさ、美味しいなどの前向きな気持ちがドライブするような時間を生活に組み込んでおくことが、とても大切なポイントだと思います。
上医は国を医す
「中医は人を医し、下医は病を医す」と続く、ご存知『小品方』(陳延之)にある有名な一節です。 当コラムの第一回目にも記したとおり東洋医学を志す私たちは、『医』という漢字の訓読みが「いやし」であるということを知っていますから、「上医は国をいやす」と読むことができますね。
『癒』という漢字は、「床に伏せてしまうような辛さ+心から+抜き出す」という造りになっていることから、転じて「飢えや心の悩みなどを解消する」という意味で使われています。 このことから腕の良い医師や本質的な医療、あるいは質の良い施策は国家を安定させるという指摘であることが読み取ることができるでしょう。
癒しといえば『癒し系』という表現でよく使われているように、「心を和ませるような雰囲気や効果を持つ一連のもの」という意味になります。 課題を解決するために正義と正義が衝突する場面がありますが、総論賛成&各論反対という信念対立を続ける限り話しは前に進みません。 むしろ和することで持続的な意見交換が交わされ課題解決へ至ることができるという真理は、遠く飛鳥時代から続く「和をもって尊しとなす」という聖徳太子の言葉にあるとおりです。
長く続いた乱世を生きた老子の思想に学び、感情の起伏と常態化にフォーカスを当てた内因論から始まり、心と身体を調和させることで未病を治すことを旨とし、幸福な人生を歩むことを求めた東洋医学は、人にも社会にも優しい生き方を提示します。
医を志した先人たちが残した「病を診るのではなく、人を診る」や「一病息災」という言葉は、病とですら戦わず、すべてを包含するのが鍼灸師の立場であると諭しているような気がします。争わず、逆らわず、小川がせせらぐように、微風が吹き抜けるような心地よい生き方を提案することが私たちの務めなのかもしれません。
私たち鍼灸師は、刺されば痛い鍼を痛くなく刺すことができるし、燃えれば熱い灸でホカホカさせることもできます。 このような学と術を駆使して、自律神経を正常な状態に導き、恒常性を働かせ、免疫機能を賦活し、DMNのスイッチをONにして、セロトニンやオキシトシンで生理学的に幸福な状態へ誘ってしまうことができるのです。
未だにソーシャルインパクトを与えるほどの受療率には至りませんが、それでも私が開業をした20年前とは隔世の感があるほどに鍼灸師の在り方が変わりました。個人開業をしている鍼灸師や病院勤務をしている鍼灸師、往診、教育機関、ホテルやリトリート施設など様々な場面に活躍の場が広がっています。各々が日常業務に励みながらも「幸福感をお届けする」というメッセージを発信し続ければ、いつか日本の幸福度を上げるための重要なメンバーになることでしょう。 ぜひ皆で、Well-beingというムーブメントを追い風として受け止めましょう。
【第1回】Well-beingという考え方
【第2回】Well-beingが注目される理由
執筆

中根 一(なかね・はじめ)
株式会社Fiero 代表取締役
鍼灸Meridian烏丸 代表
明治国際医療大学 客員教授
明治東洋医学院専門学校 非常勤講師
大分医学技術専門学校 非常勤講師
経絡治療学会 理事・関西支部長・夏期大学講師
鍼術丹波流宗家 故・岡田明祐氏、岡田明三氏に師事
全日本鍼灸学会 会員
日本慢性疲労学会 会員
ウェルビーイング学会 会員
日本養生普及協会 会員
地域共創 プロジェクトマネージャー
ラグジュアリーホテル オンコールプロジェクトマネージャー
著述家
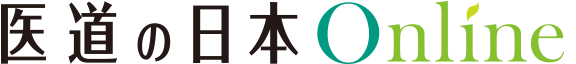
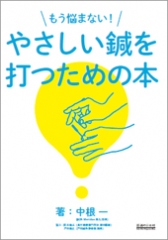
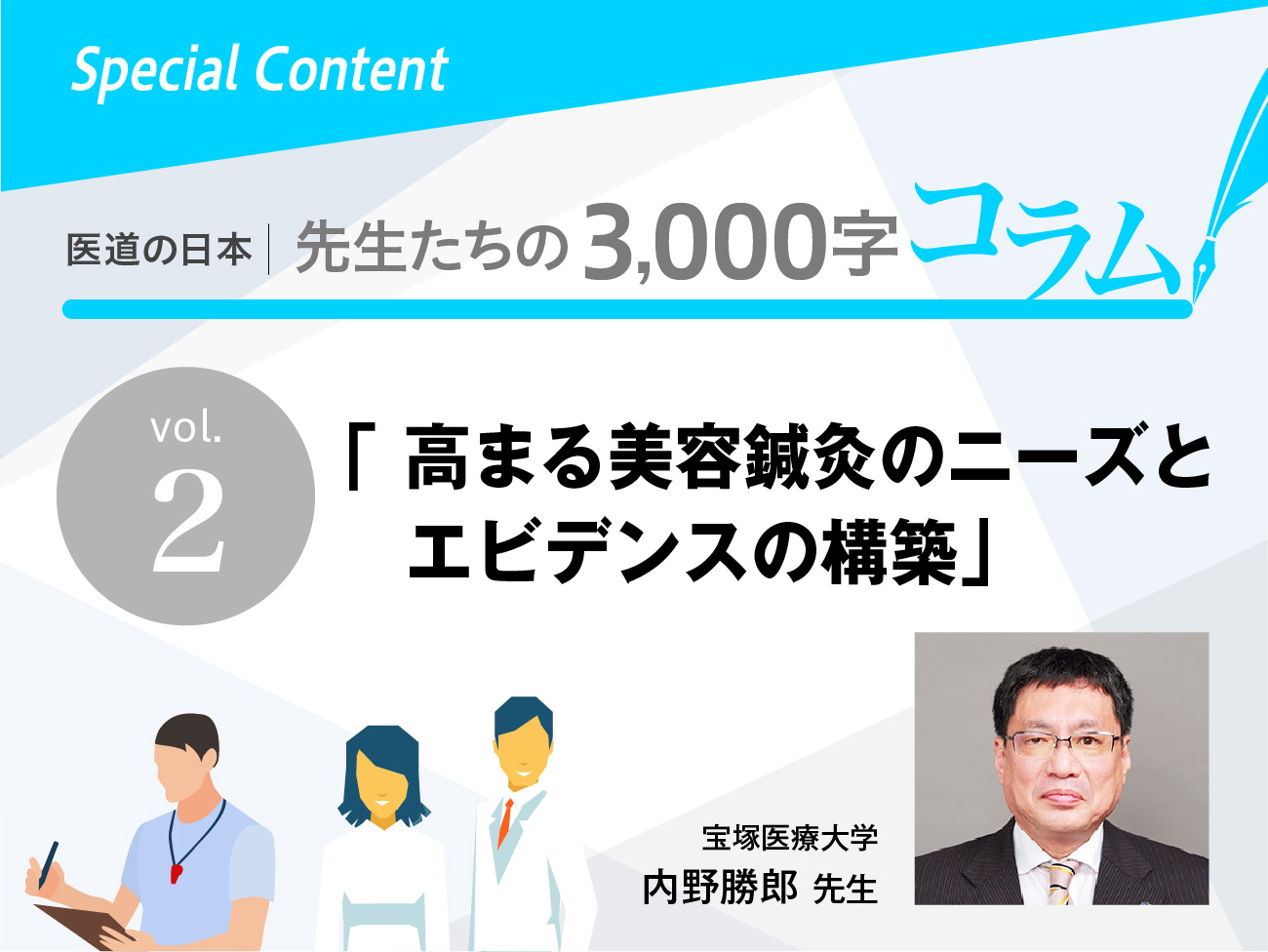
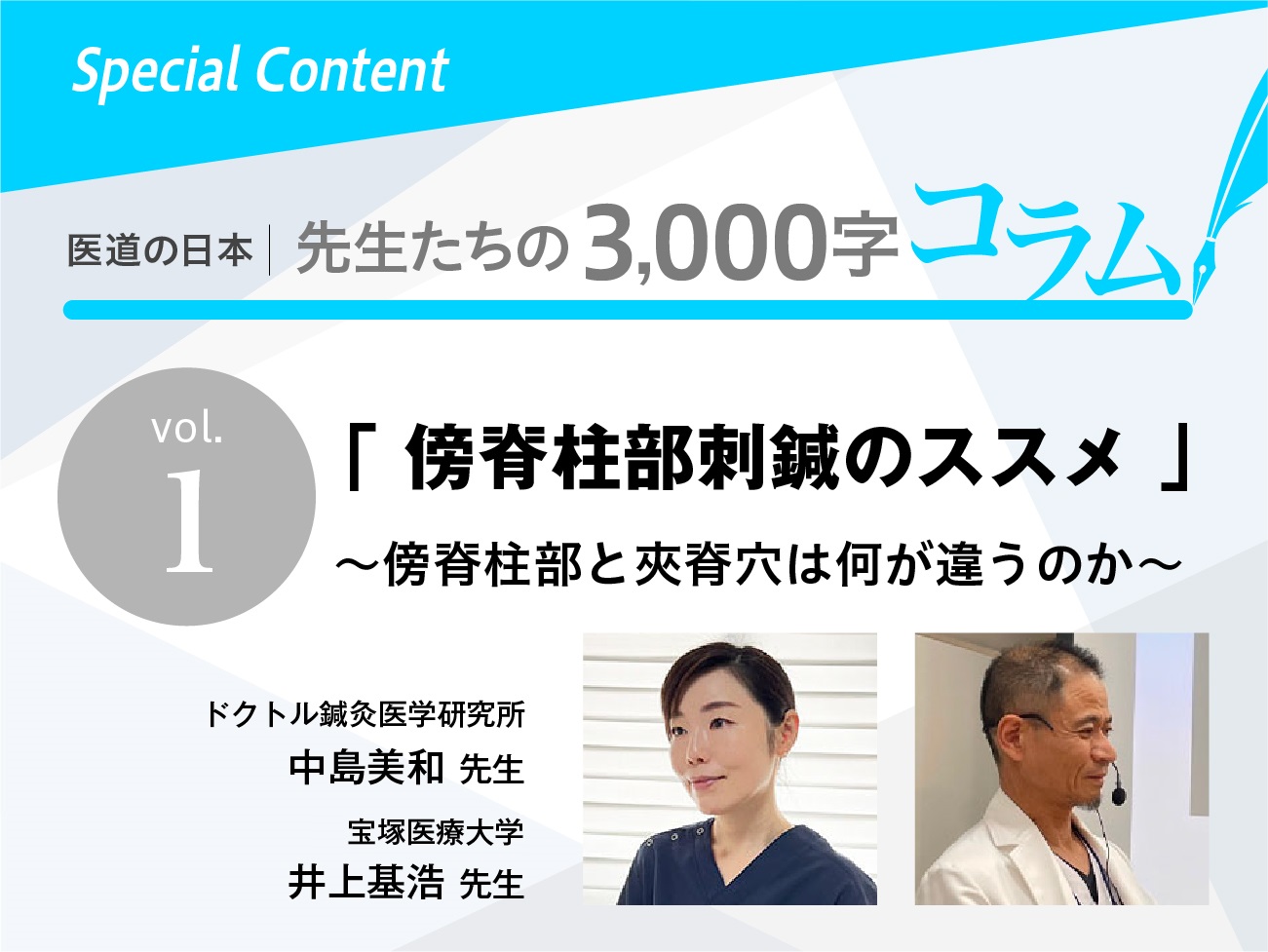
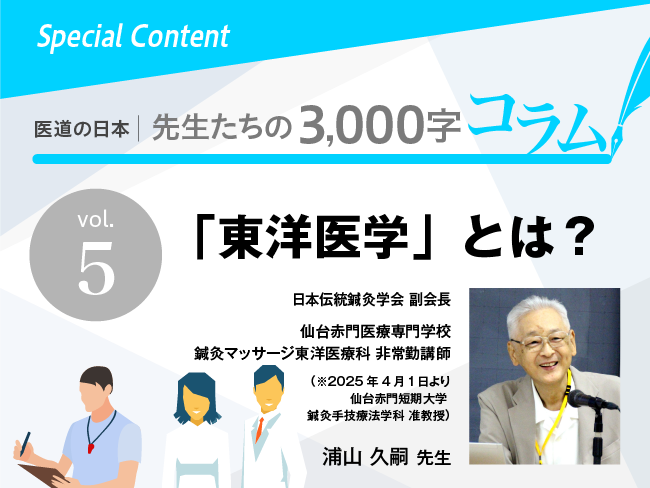

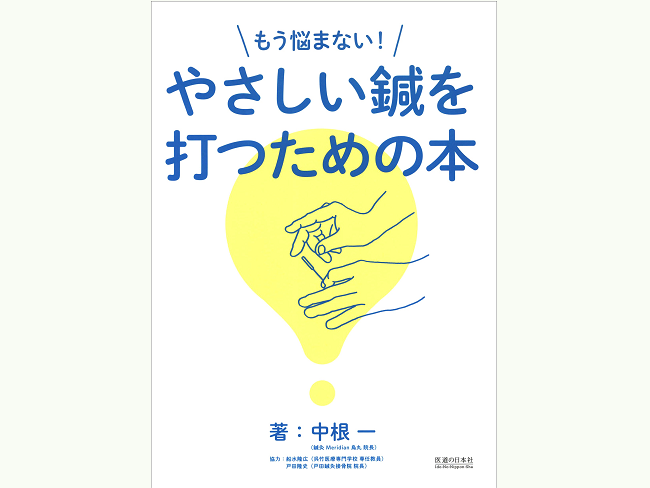
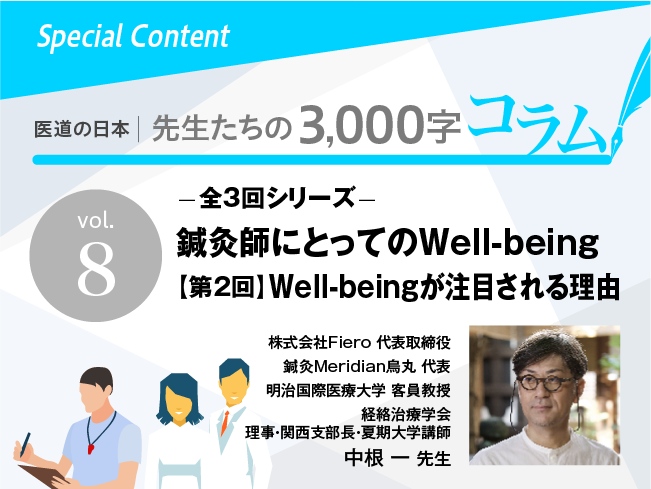
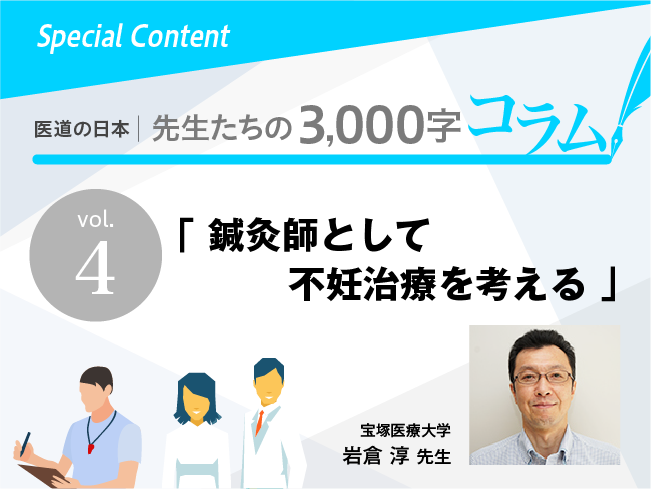
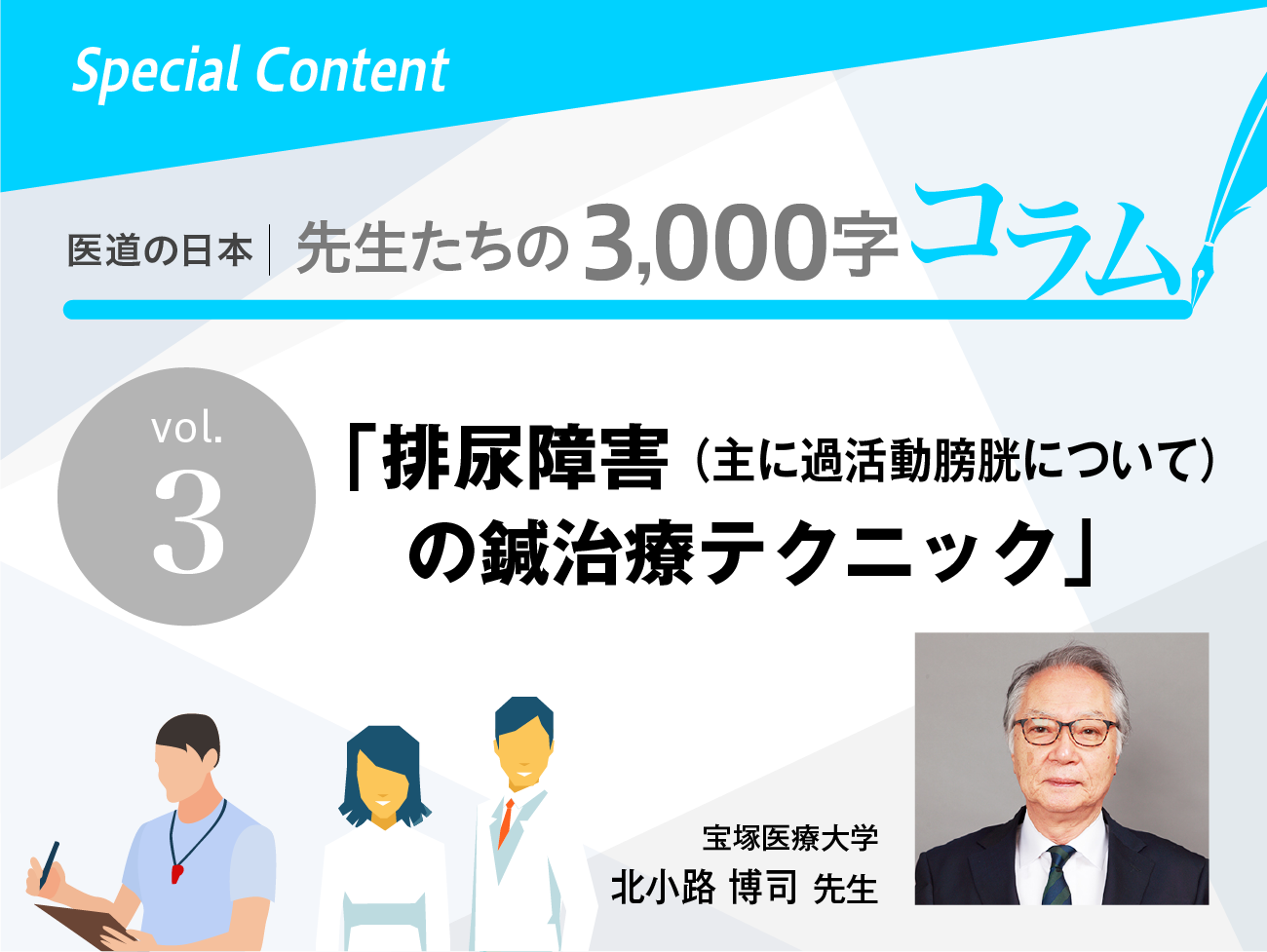
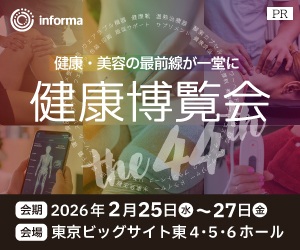






















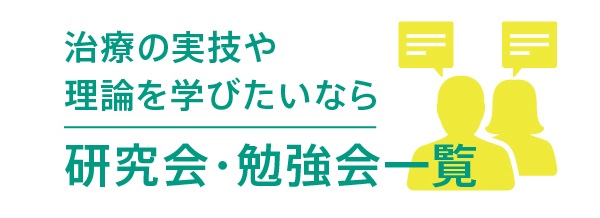
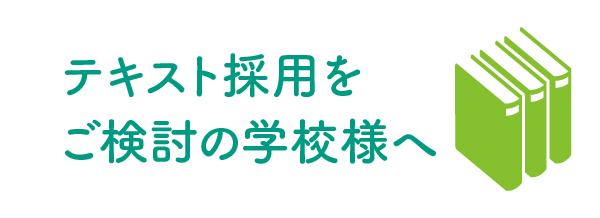
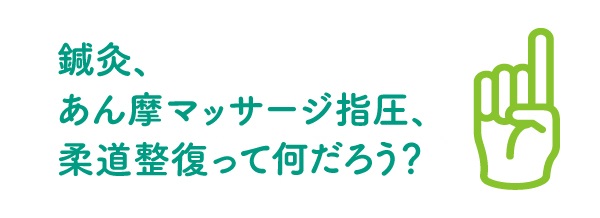
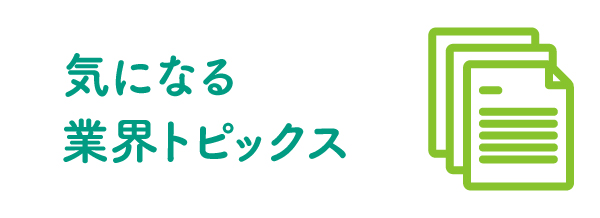


![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)