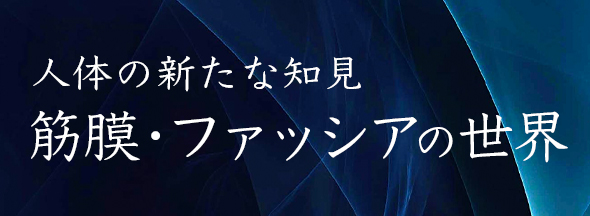第20回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会 inいばらき Tsukubaレポート

2025年10月4日、5日の2日間にわたり、茨城県の研究学園都市、つくばにて第20回 日本鍼灸師会全国大会 inいばらき Tsukuba が開催された。大会テーマは「求められる鍼灸・求める鍼灸 ―鍼灸と緩和ケアのコラボレーションを茨城から発信!!―」。本大会では、鍼灸が果たすべき役割を多角的に見つめ直し、緩和ケアとの連携を通してその可能性と未来を探ることを目的に、さまざまな講演やシンポジウムが行われた。受付での現地参加者は2日間で合計264人。来賓や演者、市民公開講座一般参加者を含めると、JTB報告では370人超となった。
目次
開会式
開会式では、大会会頭の中村聡氏(本会会長)が、現代社会における鍼灸師の役割について、まず、少子高齢化の進行により高齢者が増え、支える世代が減っている現状を挙げ、こうした時代だからこそ鍼灸師の力が求められていると述べた。近年では医師が鍼灸師との連携を模索し始めており、医療の中で協働する動きが広がっていることから、鍼灸の有効性を示し、国に理解を得ることが重要と強調した。
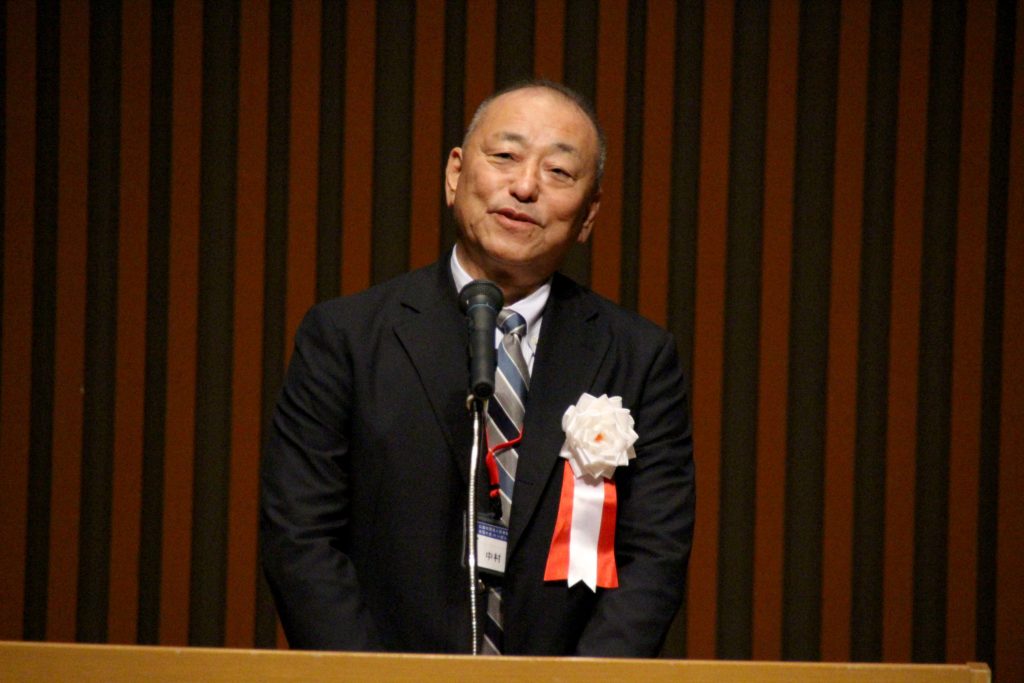
続いて、大会会長を務めた坂本一志氏(一般社団法人茨城県鍼灸師会会長)は、第20回という節目を迎えた本大会について、記念大会としての特別な意味を持ち、鍼灸を単なる治療の手技ではなく、コミュニケーションの手段と捉え、相互の交流と情報共有を通じた新たな可能性について言及した。

その後、関係団体をはじめ、茨城県知事や厚生労働省からも多くの祝辞やビデオレターが寄せられた。


学術講座
学術講座「不妊鍼灸の手技の国内標準化を目指して」にて三瓶真一氏(一般社団法人福島県鍼灸師会会長)が登壇した。まず冒頭で、2021年4月までの女性不妊症に対する鍼治療の関連研究などデータベースからの検索で、真の鍼治療群、プラセボ群、無治療群の27の研究を比較した結果、鍼治療群は臨床妊娠率(CPR)および生児出生率(LBR)のいずれにおいても有効であることが示されたと報告。しかし、細かく見ると強いエビデンスとして、判断するには弱いと指摘。また文献に関しては海外、特に中国式鍼灸や耳鍼などが中心であり、日本式の低侵襲かつ繊細な鍼管使用手技は受け入れられない手技が多かったと推測され、日本国内における不妊鍼灸は、流派や手技の多様性が大きく、他の疾患に対する鍼灸でも共通手技が少ない状況であると私見を述べた。国内での研究論文が少ない理由として、不妊症が学会で十分に取り上げられなかったこと、開業鍼灸院での対応が一般的であり研究機関での臨床データが蓄積されにくかったことなどを挙げ、そのため、国内発のエビデンスはほとんど存在せず、日本鍼灸による不妊治療の科学的根拠は十分に示されてこなかったという。こうした背景もあり、2012年に不妊鍼灸ネットワークが設立され、2024年には不妊症に対する標準的鍼灸治療法の開発と普及が進められたと振り返った。JISRAM(日本不妊鍼灸標準化研究会)は現段階での標準治療を提唱しており、卵巣機能改善や採卵成績向上には陰部神経鍼通電法や三陰交~地機鍼通電法を、子宮環境改善や胚移植での妊娠率向上には中髎穴刺鍼法を推奨。刺鍼点、刺入深度、低周波置鍼療法の詳細も定められ、効果の均一化が図られていることを伝えた。講演の最後には、標準治療手技の実技披露が行われ、聴講者に向けて臨床での具体的な適用方法を供覧。標準化により、どの鍼灸院でも最低限の効果が担保され、蓄積されたデータはビッグデータとして活用され、日本鍼灸によるエビデンスが世界へ発信されていくことることが期待されると結んだ。

「YNSAイントロダクション講座~自律神経にアプローチする新しい鍼治療~」と題して講演を行った加藤直哉氏(山元式新頭針療法YNSA学会代表理事)は、2006年から2009年にかけて山元敏勝師から直接指導を受けた歩みを振り返りつつ、YNSA(山元式新頭針療法)の特徴と治療効果について解説した。YNSAは整形疾患、脳神経疾患、婦人科疾患、内臓疾患に対して有効であり、対面座位で施術可能かつ修得が簡便である点が大きな特徴であるとし、また、ブラジル、ドイツ、ハンガリー、イタリアなど海外への普及が進んでいることに着目し、国内での普及状況についても論じた。さらに加藤氏は、YNSA学会の目的として、鍼灸師、医師、歯科医師、獣医師に山元敏勝師の正しいYNSAを伝えること、そしてさまざまな臨床経験や知識を集積・コラボレーションし、YNSAを進化させ続けることの二点を挙げた。本講演では、診断の流れや基本的な治療法についても触れられ、YNSAの理解を深める内容となった。

「北辰会方式の鍼灸治療の実際と、医師―鍼灸師の連携について」の講演を行った竹下有氏(一般社団法人北辰会学術副部長)。北辰会が提唱する鍼灸治療方式について、北辰会方式の特徴は、まず、理論の基本として現代中医学を取り入れ、病態の把握には中国伝統医学独自の診察法である四診を活用し、多面的に症状や体の状態を評価する(四診合参)。次に、日本の江戸期伝統鍼灸古流派の技術を応用的に取り入れ、ごく少数の配穴による治療を主としている点、さらに、独自の刺鍼技術である撓入鍼法を用いることが提唱されていると紹介。講演では、解説に加え、実際の刺鍼手技のデモンストレーションが行われ、北辰会方式の治療プロセスや技術の特徴を視覚的に理解できる内容となった。

緩和ケア講座
「日本の支持・緩和医療における鍼灸の現状と展望」と題したセッションでは、医療現場における鍼灸の役割と今後の展開について講演と討論が行われた。はじめに高久秀哉氏(水戸済生会総合病院 緩和ケア内科 主任部長)による基調講演「緩和ケアについて―医鍼連携を目指して―」が行われ、講演内容を「緩和ケアについて」「緩和ケアと鍼灸について」「医療連携の進め方」の3点に分けて解説。まず、緩和ケアとは患者の苦痛を取り除き、患者とその家族が自分らしく生活を送れるよう支援するケアであると示したうえで、がん患者が抱える痛みについて、がんそのものによる痛み、長期臥床による腰痛などの関連痛、術後痛、変形性関節症などの併発痛があると説明した。また、身体的苦痛に加え、経済的な負担などの社会的要因、うつ状態などの精神的要因、死の恐怖といったスピリチュアルペインが存在することにも触れた。緩和ケアは医師だけでなく、薬剤師、看護師、医療ソーシャルワーカー、理学療法士、管理栄養士など多職種が関わるチーム医療であり、全人的かつ継続的な支援が必要と述べた。その中で鍼灸は、症状緩和や副作用の少なさ、心身双方への作用などを持ち、西洋医学を補完する治療として有効に介入できるとした。
山口智氏(埼玉県鍼灸師会会長/埼玉医科大学医学部客員教授)が指定発言「がん専門病院の鍼灸治療と、開業鍼灸師としての医療連携の試み」について講演した。発表の最後に、「Take home message」として、聴講者に向けてまず、がん患者の痛みや浮腫、倦怠感、食欲不振、便秘などの症状に対して鍼灸治療が有用であること。海外のガイドラインにおいては一部で鍼灸治療が推奨されているものの、日本国内における推奨事例は極めて少ない現状であること。さらに、支持・緩和の専門医と高い専門性を有する鍼灸師が連携し、診療や研究を推進していくと伝え、「日本からのエビデンスを!」との力強いメッセージで締めくくった。
堀口葉子氏(国立がん研究センター中央病院緩和医療科)は、「がん専門病院の鍼灸治療と、開業鍼灸師としての医療連携の試み」の講演の中で、医療連携(病院・地域医療)の課題として、病院や組織の仕組みを理解すること、病態を把握し、共通言語で説明したうえで紹介状を作成すること、さらに状況や目標を定期的に情報共有するためのコミュニケーション力を重視すべき点として示した。また、鍼灸における課題としては、がん医療や緩和ケアに関する教育機会が不足していること、多職種や患者に対して鍼灸治療を理解してもらうための努力が必要であると伝えた。
武田真輝氏(市立砺波総合病院緩和ケア科)は「緩和ケア科での鍼灸」について発表を行い、緩和ケア科の対象となる事例や目指すところ、スタッフの役割を述べ、最後に緩和ケアのスタッフとの相談を通して見えてきたものとして、専門的緩和ケアだけが緩和ケアではなく、ポイントは連携であると展開した。


特別講座
特別講座「鍼灸師はこのままでよいのか 〜50年後、100年後の鍼灸師を語ろう〜」 鳥海春樹氏(医療法人社団健育会湘南慶育病院鍼灸科部長)と伊藤和憲氏(明治国際医療大学鍼灸学部教授)による講座が開かれ、大学における研究・教育および臨床施設の運営に携わり、長年教鞭を執ってきた両演者が、鍼灸および鍼灸師の現状と将来像について、立場を超えてフラットに意見を交わした。議論が「未病」へと及ぶと、鳥海氏は「健康診断のさらに手前に、未病を診断する仕組みがあっても良いのではないか」との考えを示した。一方、伊藤氏は、未病を“見える化”するアプリの開発に取り組んでいることを紹介し、「その可視化により、就職や結婚など人生のあらゆる場面で、その人がどれだけ健康的に、どれだけ活躍できるかを示す新たな価値になる」と述べた。そして「病気にならないための健康」ではなく、「好きなことをするための健康」という発想の転換を、東洋医学が提示できるのではないかと展望を語った。
また、鳥海氏が「鍼灸師は鍼を打てなければ東洋医学の価値は語れない」と意見を述べると、伊藤氏は「鍼の技術があることは前提だが、それだけでは患者は来ない」と応じた。患者が来院する背景には、人柄や地域における立ち位置など、人間的・社会的な要素が大きく関わっていると指摘し、「医療にこだわりすぎることで発展が停滞している現状を捉え、医療をベースとしつつも、そこにとどまらない新たな価値を追求する姿勢の重要性について論じた。最後に鳥海氏は、「鍼灸は生かさなければならない。良いものとして育てていくことが大切だ」と締めくくり、本セッションは、鍼灸の未来を考えるうえで、多くの気づきと示唆を与えるディスカッションとなった。

市民公開講座
市民公開講座「東洋医学ホントのチカラ 鍼灸の現在地と可能性」というタイトルで山本高穂氏(NHKコンテンツ制作局チーフ・ディレクター)が登壇。NHKの特番「東洋医学ホントのチカラ」やNHKスペシャル「東洋医学を“科学”する」の実際に放送された映像をスライド上映し、慢性疼痛、精神疾患、リハビリテーション、スポーツケア、免疫改善といったテーマを中心に講演を行った。その中で、社会的孤立に関して、まず予防としてソーシャルキャピタル(社会関係資本)が基本となることを伝えた。ソーシャルキャピタルとは、人々のつながりや助け合い、協調行動を促進する社会的な力のことであり、地域の健康向上や疾病リスクの低下に寄与するとされている。そこには信頼とネットワーク、一般的な互酬性の規範が関わっていることを示すと、ソーシャルキャピタルを豊かにする要素と、その中での鍼灸師の役割について、鍼灸師が持つ食生活や医療に関する知識が患者や友人、その周囲の人々へと伝わり、地域全体の健康意識を高めるといった他人への影響(Social influence)、非公的な社会的統制(Informal social control)、集団行動(Collective efficacy)さらに、ストレスの低減(Stress buffer)を挙げ、これらの要素が相互に作用することで、地域住民の疾病リスクが低下し、健康の維持と増進につながると考えられると伝えた。鍼灸師が地域社会において果たし得る多面的な役割を明確に示しているとした。

その他講座、学生交流会、ブース展示
その他、委員会講座やランチョンセミナーも実施された。また、ホテルグランド東雲では学生交流会が開かれた。
特別講座
「戦略より戦術の実技研修 見えにくい方への指圧指導の現場から」
大場裕之氏(公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会副会長・広報委員長)
委員会講座
「“あはき療養費”初めての人・学生のための<基礎編>」
平野健一氏(公益社団法人日本鍼灸師会業務執行理事・健保委員長)
「毎月の療養費請求、改めてルールの確認<実務編>」
小林潤一郎氏(公益社団法人日本鍼灸師会副会長)
シンポジウム「多職種・地域連携―現場からの声を聴こう」
「地域診療における鍼灸師の可能性」
岸奈治郎氏(岐至漢方クリニック)
「多職種・地域連携―現場からの声を聴こう」
森久紀氏(一般社団法人茨城県介護福祉士会会長)
菅野幸治氏(公益社団法人日本鍼灸師会業務執行理事・地域ケア委員長)
第2回スポーツ鍼灸トレーナー研修会
「下肢障害に対する足部の評価法(FPI)の実践」
石川亮一氏(スポーツ鍼灸委員会副委員長)
「あはき法改正に向けて」
中沢良平氏(公益社団法人日本鍼灸師会法人管理委員会・あはき法改正推進チーム)
ランチョンセミナー
「我々は何をすべきか~鍼灸理療実践研究会からの提案~」
中村一徳氏(京都なかむら第二針療所・栗東鍼灸整骨院鍼灸部門総院長)
「緩和医療における鍼灸治療の実際―がん専門病院における臨床から―」
星野直志氏(神奈川県立がんセンター東洋医学科非常勤鍼灸師)

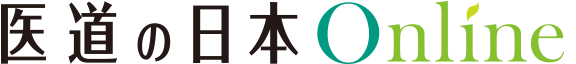



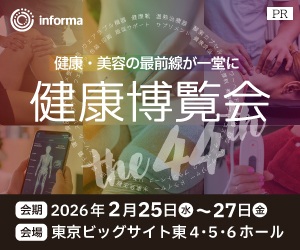























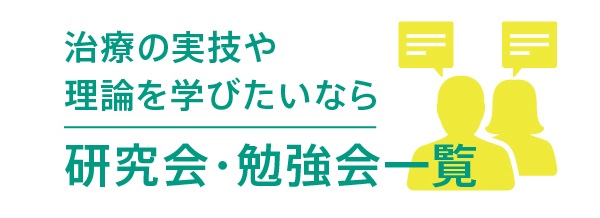
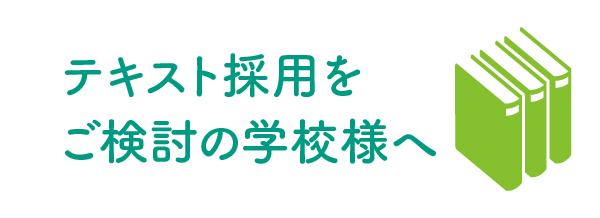
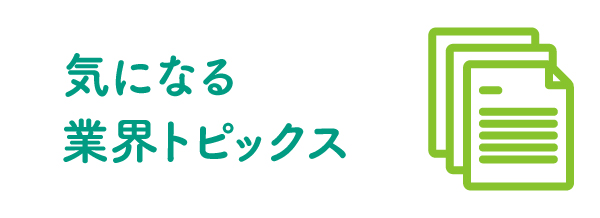
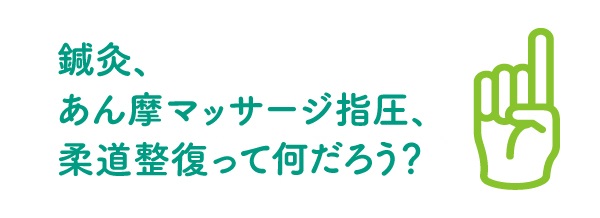

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)