ファシアからの、炎症と痛みの解説
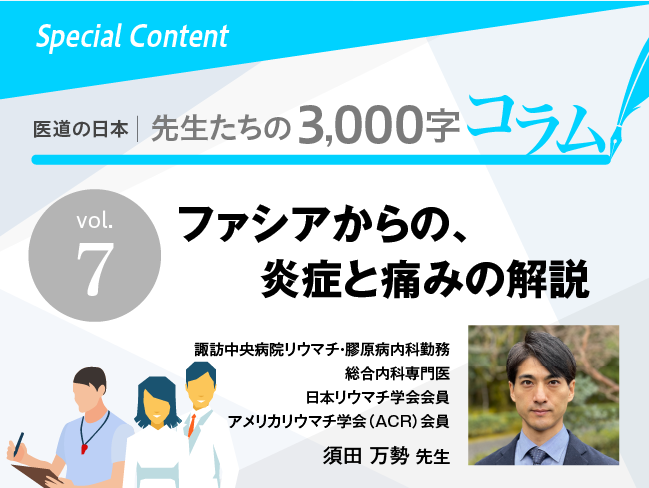
はじめに 痛みの原因を問い直す
国際疼痛学会(IASP)によれば、痛みの機構は①侵害受容性疼痛 ②神経障害性疼痛 ③痛覚変調性疼痛に分けられる。近年、痛みの治療は②や③を標的とした薬物療法に傾倒しているように思われる。しばしば終わりがなく「薬漬け」の患者さんを量産する可能性がある。我々は①の侵害受容性疼痛にもう一度目を向け直し、痛みの局所に何が起こっているかを検討する必要があるのではないだろうか?
本稿では、特に「ファシア」という組織の異常に着目し、痛みの「原因」に対する介入を検討する。
1.「ファシア」との出会い
私は2018年に監訳した「閃めく経絡」という本の中で、ファシアという概念に出会い、それが東洋医学と西洋医学を結ぶ解剖学的架け橋になるかもしれない、という仮説に魅了された。ファシアとは、全身にある臓器を覆い、接続し、情報伝達を担う線維性の立体網目状組織。臓器の動きを滑らかにし、これを支え、保護して位置を保つシステムである(https://www.jnos.or.jp/for_medical)。コラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸などを含み、柔軟性と強度を兼ね備えている。
また、ファシアには自由神経終末が豊富に含まれており、疼痛の知覚に重要な役割を果たしている。「閃めく経絡」では、ファシアのピエゾ効果と氣、発生学的な視点でみた経絡経穴との関係性など、目を開かれるような視点が満載で、監訳者の私自身が一番勉強をさせていただいた。以来、ファシアという観点から患者さんを観察しながら、新しい疼痛治療を模索している(その詳細は「痛み探偵の事件簿」という本に纏めた)。
2.痛み(特に慢性疼痛)とファシアの関連
ファシアは、構造的・生化学的・細胞レベルの相互作用を通じて、痛みのメカニズムに多面的な影響を及ぼす。 特に、炎症や線維化が進行する微小環境において、ファシアは機械的特性の変化、炎症への免疫応答、神経系との相互作用、水分動態などを介して痛覚に影響を与え、慢性疼痛を持続させる複雑な経路を形成する(Kodama, Yuya, et al. “Response to mechanical properties and physiological challenges of fascia: diagnosis and rehabilitative therapeutic intervention for myofascial system disorders.” Bioengineering 10.4 (2023): 474.)
① ファシアの機械的特性の変化
ファシアの粘弾性により機械的ストレスが分散されるが、線維化(コラーゲン過剰沈着)による病的な硬化が生じると、ファシア内の自由神経終末をはじめとした痛覚受容器(nociceptor)への機械的ストレスが増加する。
② 微小環境の炎症性変化
ファシア内の炎症により、下記のような変化が起こりうる。
- マクロファージや線維芽細胞が、TGF-β1やIL-6といった炎症性サイトカインを放出し、痛覚受容器の感作を促進するとともに、線維化を進行させる(表1)。
- 慢性炎症により、線維芽細胞のコラーゲン産生遺伝子が活性化し、一方でヒアルロン酸(HA)の分泌が低下し、ファシアの滑走性を低下させる。
- 炎症を伴う筋膜では、自由神経終末や痛覚受容器の密度が増加し、痛みのシグナルが増強される(例えば、炎症を伴う胸腰筋膜(thoracolumbar fascia)では、痛覚受容器が伸長し、わずかな機械的刺激にも反応しやすくなることが報告されている)。
表1.ファシア内の細胞と線維化、疼痛との関連
| 線維化における役割 | 痛みへの関与 | |
| 筋線維芽細胞(Myofibroblasts) | 機械的ストレスにより線維芽細胞から分化し、コラーゲンや細胞外基質タンパクを分泌する。 | 組織の収縮や硬化を 生む。 |
| SPP1⁺ 陽性マクロファージ | SPP1からのシグナル伝達により、線維芽細胞の活性化を促進させる。 | 間接的に細胞外基質の 沈着を増加させる。 |
| 細胞外基質様マクロファージ ECM-like macrophages | コラーゲンやプロテオグリカンなどを分泌する。 | ファシアの肥厚に関与 する。 |
(Zhao, Weizhi, et al. “Identification of pro-fibrotic cellular subpopulations in fascia of gluteal muscle contracture using single-cell RNA sequencing.” Journal of Translational Medicine 23.1 (2025): 1-16.)より筆者作成
③ 神経とファシアのクロストーク
ファシアは自由神経終末を高密度に含んでおり、ファシアと神経が下記のようにフィードバックループを形成する。
- ファシア内の細胞外マトリックス(ECM)の線維化やヒアルロン酸(HA)の粘度変化により自由神経終末がトラップされ、痛みを引き起こす。
- (ファシアに多く存在する)交感神経の活性化がTGF-β1の産生を介して線維化を促進する。
④ 水分動態と虚血
- ファシアの細胞外基質の脱水が起こると、ファシアの粘性が高まり、栄養の分配や老廃物の排出が阻害される。それにより局所的な虚血が発生し、C繊維を主体とする自由神経終末が活性化される。
- 一方で、炎症による細胞外の浮腫は、ファシアの剛性を増加させ、滑走性を低下させる。また血管を圧迫するため循環が悪化し、低酸素(hypoxia)と痛覚受容器の感作が悪循環を形成する。
3.ファシアハイドロリリースによる除痛
ファシアに対しての治療的介入は、リハビリテーション、鍼灸(dry needling)など様々な方法があるが、我々のグループは生理食塩水などを用いたエコーガイド下ファシアハイドロリリースを行い、その有効性を実感している。実際、慢性痛の代表疾患である肩関節周囲炎に対し、烏口上腕靭帯に対するエコーガイド下ファシアハイドロリリースの有効性を我々が報告した(Kimura, H., Suda, M., Kobayashi, T. et al. Effectiveness of ultrasound-guided fascia hydrorelease on the coracohumeral ligament in patients with global limitation of the shoulder range of motion: a pilot study. Sci Rep 12, 19782 (2022).)ほか、腰痛(Kanamoto, H. et al. Effect of ultrasound-guided hydrorelease of the multifidus muscle on acute low back pain. J. Ultrasound Med. 40, 981–987 (2021).)、膝関節の術後痛(Machida, T., Watanabe, A. & Miyazawa, S. A new procedure for ultrasound-guided hydrorelease for the scarring after arthroscopic knee surgery. Cureus 12, e12405 (2020).)など様々な領域の疾患に対してもエビデンスが出てきている。
ファシアハイドロリリースによる除痛メカニズムは未だ証明されていないが、前項で述べた痛みのメカニズムを踏まえた仮説として、
・線維化による硬化の軽減や粘性の軽減による、痛覚受容器への機械的ストレスの減少
・ファシアの水分量の回復による、局所的な虚血の改善
などが考えられている。
諏訪中央病院リウマチ膠原病内科ではハイドロリリース外来を創設し、整形外科、東洋医学科など他科との連携の中で筋骨格の疼痛に対する多職種連携治療を展開している(https://www.suwachuo.jp/shinryo/rheumatology/)。
おわりに 「痛み探偵」の事件簿は続く
我々臨床医は、目の前の患者さんを観察することで次の時代の医学の扉を開く役割を持っている。「薬漬け」の痛み治療にならないように、ファシアというキーワードで痛みを持つ患者さんにアプローチし、まだまだ不明な点が多い侵害受容性疼痛に対して、ファシアの異常を改善する治療を行っていきたい。
執筆

須田 万勢(すだ・ませい)
聖路加国際病院リウマチ膠原病センターを経て、2019年より諏訪中央病院リウマチ・膠原病内科勤務。
総合内科専門医
日本リウマチ学会会員
アメリカリウマチ学会(ACR)会員
日本リウマチ財団認定医
日本内科学会認定医
日本東洋医学会会員
須田先生「監訳」「訳」の弊社出版書籍ご紹介
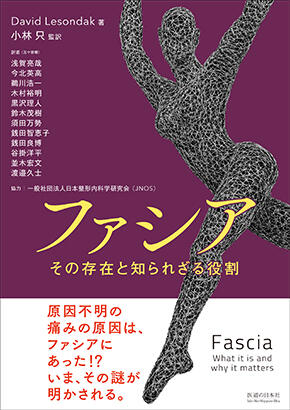
ファシア
―その存在と知られざる役割―
著 : David Lesondak
監訳 :小林只
訳(五十音順) : 浅賀亮哉 今北英高 鵜川浩一 木村裕明 黒沢理人 鈴木茂樹 須田万勢 銭田智恵子 銭田良博 谷掛洋平 並木宏文 渡邉久士
協力 : 一般社団法人日本整形内科学研究会(JNOS)
須田先生の著書のご紹介
痛み探偵の事件簿
―炎症?非炎症?古今東西の医学を駆使して筋骨格痛の真犯人を暴け!―( 日本医事新報社)
著:須田万勢、監修:小林只
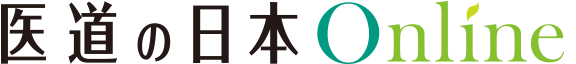
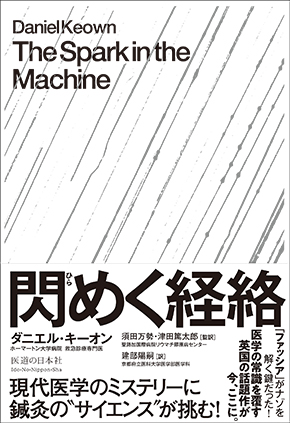

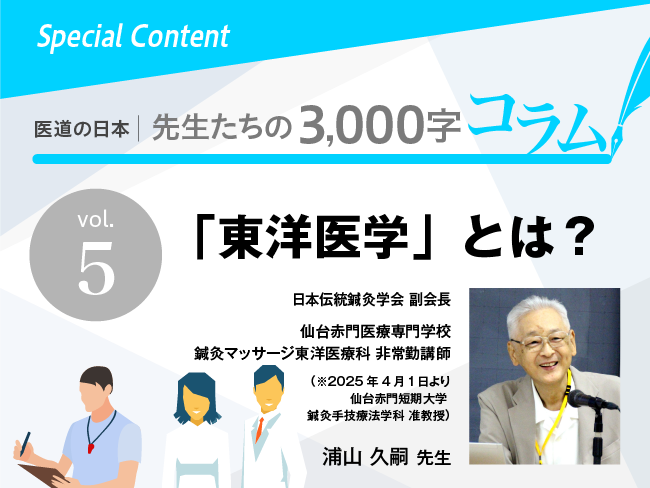
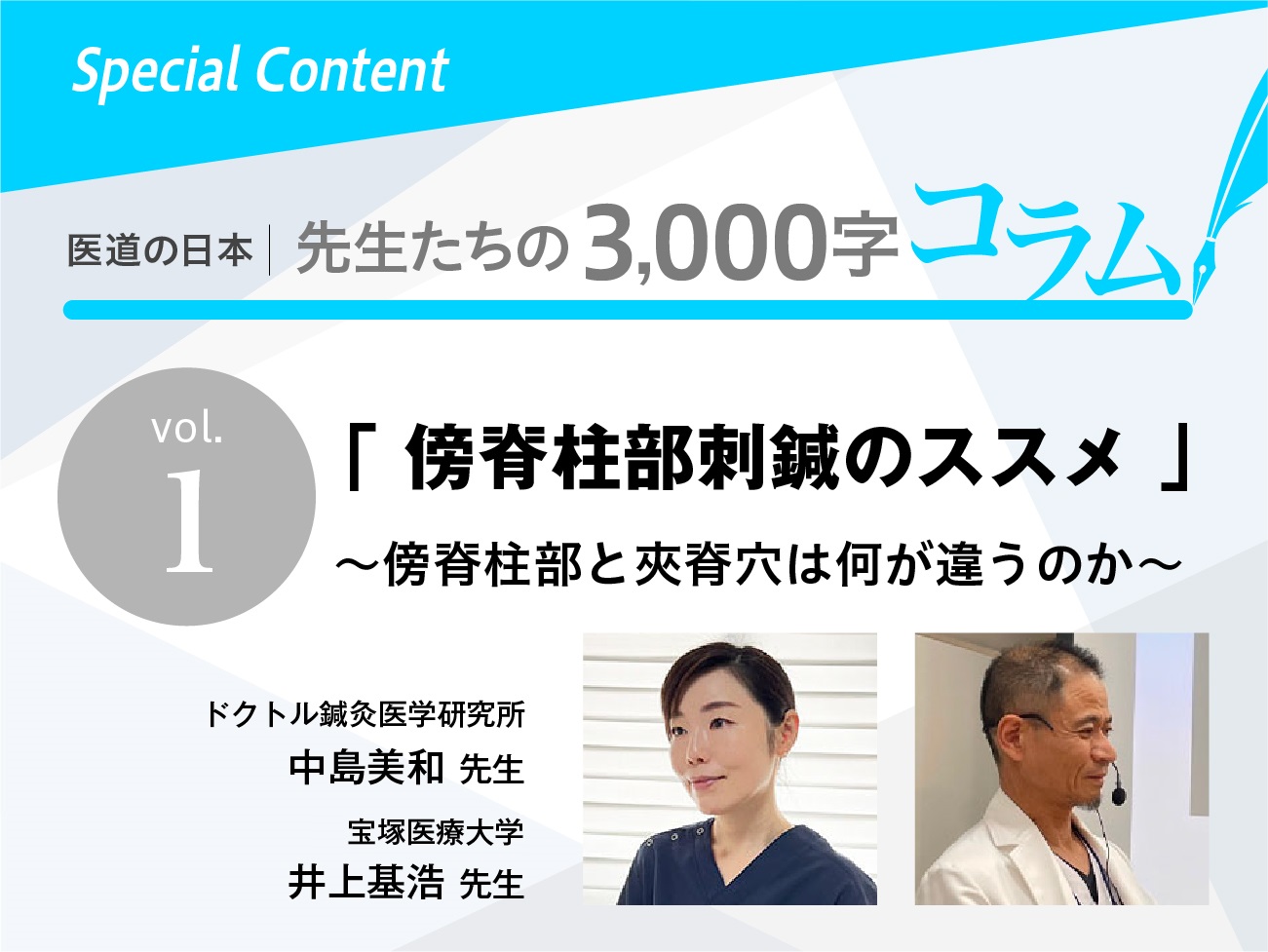
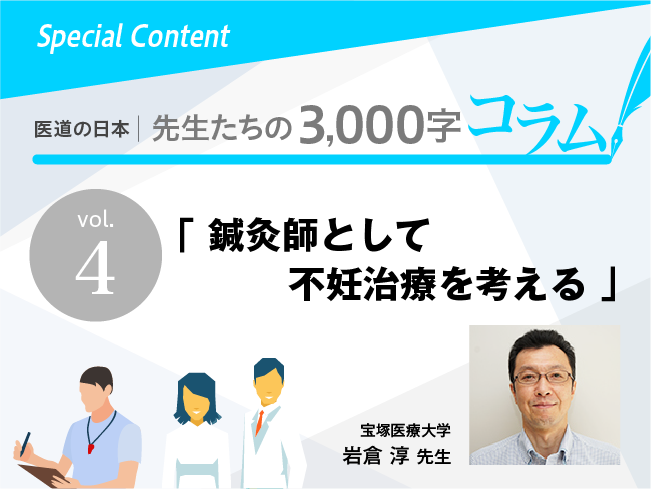


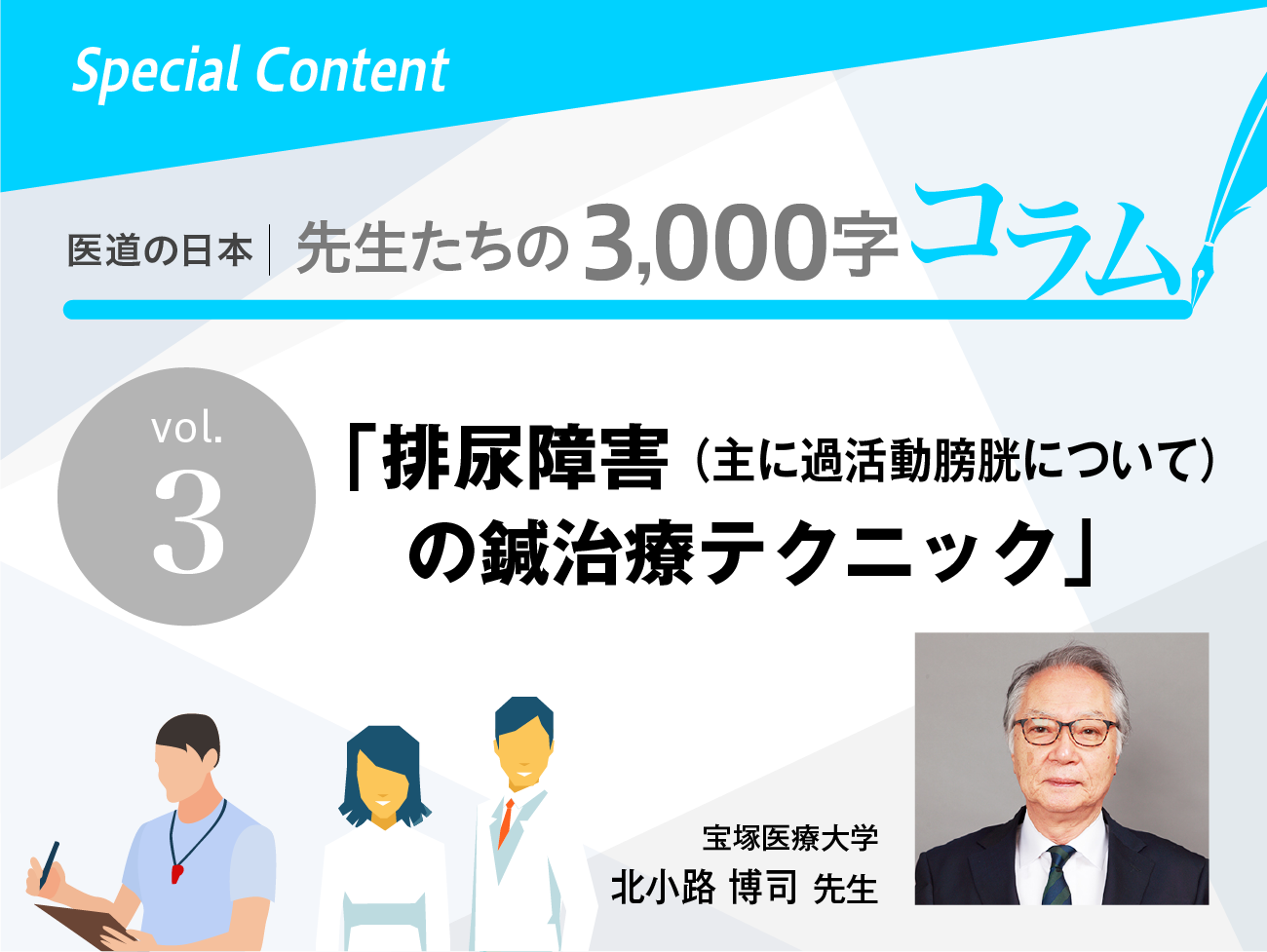
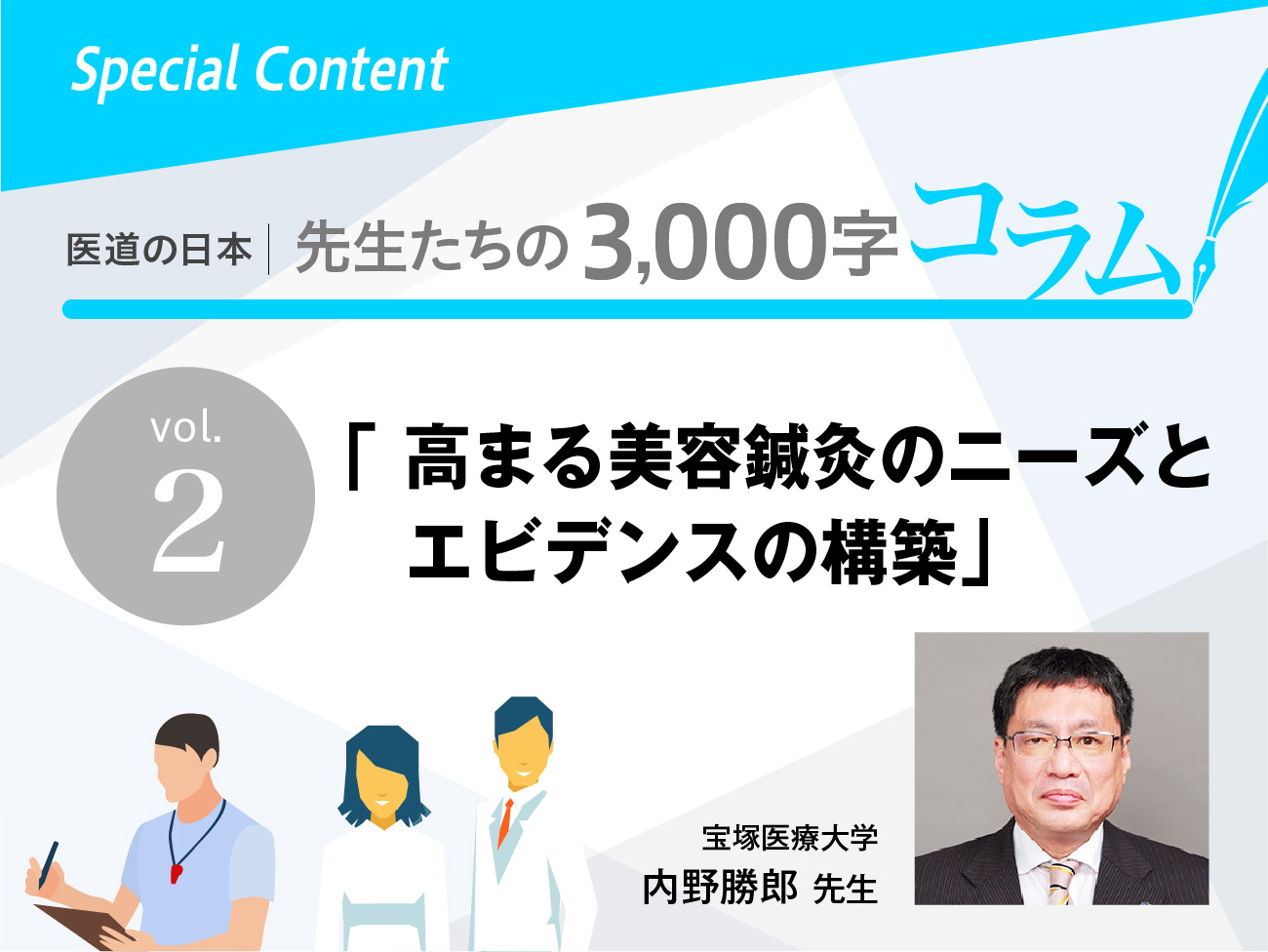

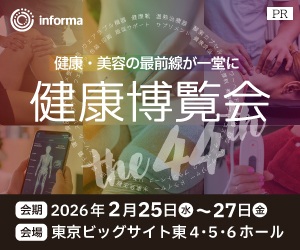


















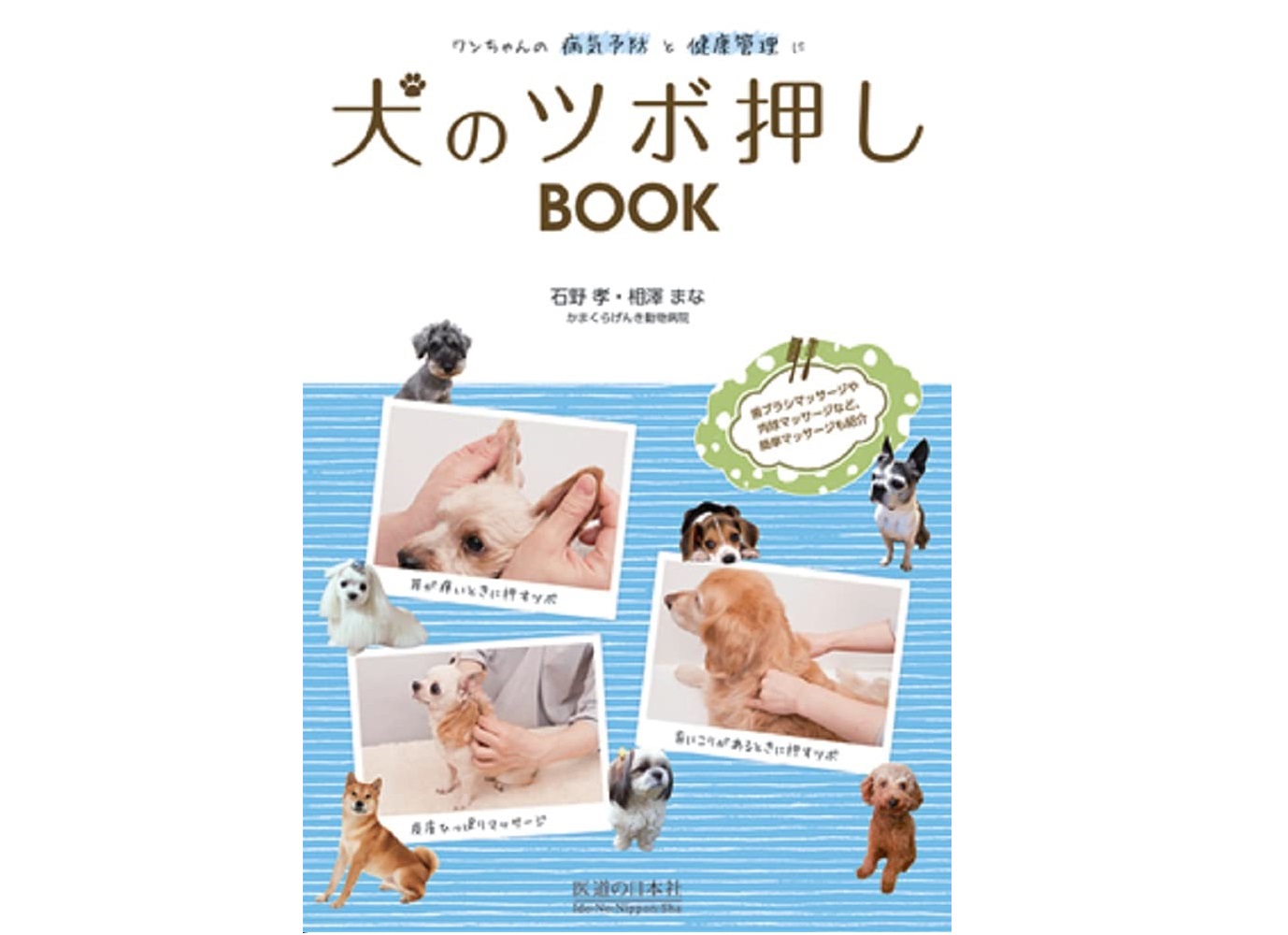



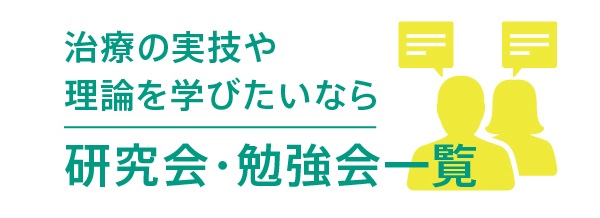
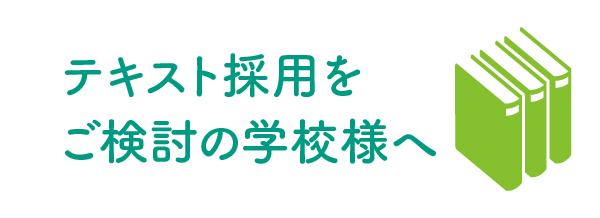
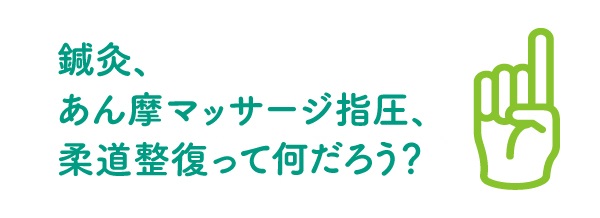
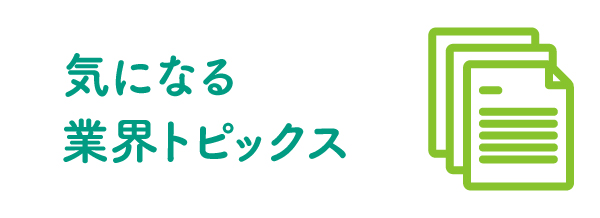




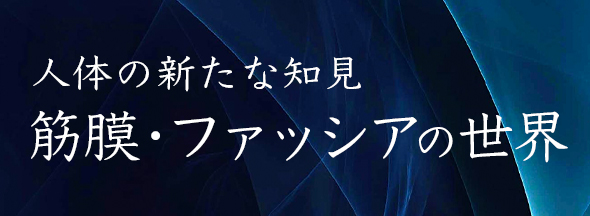
![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)