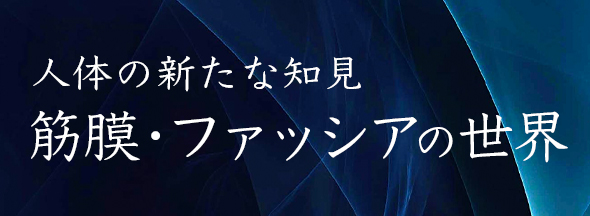触診の大切さと触診のコツ〜第1回〜(全2回)
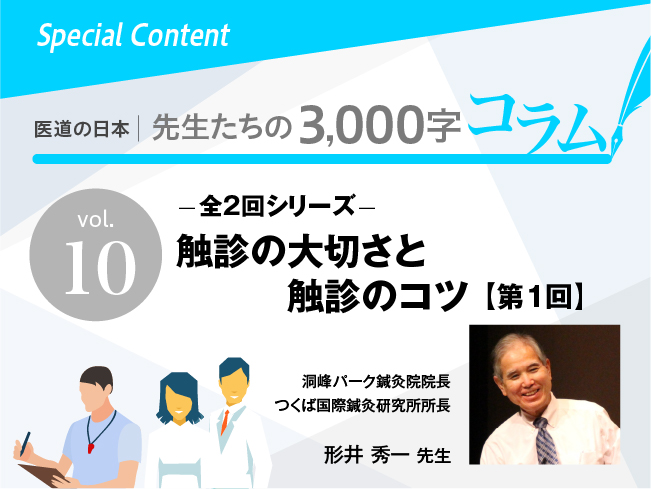
はじめに
鍼灸学の診察法には四診法(望診、聞診、問診、切診)があり、その一つである「切診」は、脈診、腹診、切経、候背診が代表的なものである。切診の際に、それぞれが対象とする体表の部位は異なっているが、それらは、人体の体表に、主に、手掌や手指で触れて、体表の情報を把握するいう意味では、いずれも「触診」であり、「切診=触診」と言えよう。
本小論は、「触診」について述べるが、「切診」の中でも、「脈診」以外の「腹診、切経、候背診」について述べる。
触診の役割
1.診察における体表情報の収集
さて、臨床における医療行為は、「診察、診断、治療」の行程で成り立っており、「触診」は、「診察」の一方法である。
そのため、「触診」によって体表から得られる「診察」情報を「診断」に役立たせることが、「触診」の重要な役割となる。臨床の過程における触診の役割は、診察・診断のための情報収集である。
しかし、鍼灸治療においては、「触診」は、「診察」の際の役割に止まらず、「治療」の全過程を通した役割がある。
2.治療の過程における触診の役割
「触診」が、「診察」の過程のみならず大切な役割を果たすのは、鍼具と灸具を用いて、生体の適切な体表部に刺激を与え、生体の治癒機転に働きかけて、生体が陥った病的状態を改善する「治療」の過程においてである。その「治療」の段階で最も重要なことは、治療対象となる「部位」、すなわち、刺鍼部位と施灸部位を確定し、その部に鍼灸治療を行うことである。その鍼灸治療部位を確定するために、「触診」が重要な役割を果たすことになる。
だが、「診察」によって、治療のための「経穴」が確定したのだから、治療過程では「触診」はさほど重要ではなく、確定した経穴部位(文献1)として定められている部を教科書通り取穴して、その部位に刺鍼、施灸をすればそれで良いと考えるかも知れない。
しかし、診察で確定した部は、飽くまでも、理論上の治療部(多くが経穴部位)である。実際の臨床の際には、理論上の経穴部位およびその周辺で、患者の体表に表現されている問題(「反応」)を探して、そこに鍼灸刺激を与えることが、より適確な臨床効果を得るために必要な方法である。
(1)経穴部位周辺を立体的に触診する
さて、体表の反応を対象とする鍼灸刺激部位は、体表面のみの状態で決まるのではなく、鍼灸刺激対象となる反応組織が皮下のどれ位の深部(の位置)にあるのかも含めて、立体的・総合的に判断して位置が決められる。それには、経穴部位およびその周辺で、体表の皮膚表面および皮下の深さの両方の視点から、立体的に「触診」して、刺鍼部位を確定する必要がある。
つまり、体表面および深さを総合して、鍼灸刺激対象となる反応部位が決まる。
それは、同時に、どの太さの鍼を使用し、どの深さまで鍼を刺入するか(鍼の長さにも影響)、あるいは、どの大きさの艾炷とし、幾つの壮数とするかを決める判断材料をも提供してくれる。
このように、「触診」により「鍼灸を行う反応部を探す」(取穴する)という意味は、鍼灸刺激を与える反応部を探すということであり、反応を体表面(皮膚)上の部位と皮膚からの深さの両面から触知することである。つまり、反応の形、硬さ、大きさなどを感知し、体表面の位置とその位置での深さ、さらに周りの骨や腱、筋、反応などとの位置関係を「触診」でさぐって、把握しながら、部位を確定することが、「取穴する」ことである。
このように、刺鍼・施灸する反応部位は、皮膚上の位置のみでは決まらず、その深さをも立体的に確定することが必要であり、その確定のために「触診」が必要かつ重要である。
(2)先人の指摘
そのことは、先人達がすでに指摘しているところである。
経絡治療創設時の指導的立場にあった柳谷素霊は、「(ツボの位置が)分寸的に決定されたにしても、如上の目標がその部位になかったならば、鍼灸に応ずべき気血の往来無しと見て、その近処を指捜し、目標ある部を穴として決定するのである。」(文献2)と述べ、経絡治療学会創設メンバーの一人であった岡田明祐は、「臨床の上で顕現状態にある経穴が、骨度法で示された経穴に一致するかどうかは疑問に思うわけで、臨床的には病体状態を表している経穴をとるようにしなければならない。」(文献3)と書き残している。
また、北辰会代表の藤本蓮風が、『体表観察学』で、「取穴方法を正確に覚えて、あとは微妙な体表観察によって(広い範囲にある治療部位から刺鍼部位を;著者)決定する。そうする事で効果に雲泥の差が出ます。」(文献4)と質問に回答し、深谷灸法の入江靖二は、『図説 深谷灸法―臨床の真髄と新技術―』中の「経穴と変動穴」で「正確にツボを求めるためには、先ず標識である経穴部位を求めて、そこから、経穴反応である圧痛や硬結・陥下などの顕著に現れているところをして取穴点とすることである。」(文献5)と著している。このように、鍼灸臨床を重ねた日本の鍼灸師は、理論的に経穴が決まり、教科書通りにその経穴部位に到達したとしても、その部位に、治療に適した反応がなければ、その周囲でより適切な部を「触診」して、探して、問題の反応のある部に治療をする必要があることを共通して述べている。
また、取穴の際に、「触診」が重要であるとする記述は、古典にも見られる。例えば、『霊枢』経脈 第十に、「15絡(穴)は、実の際にはよく見えるが、虚の場合は目視できないので、上下(深部や浅部)で探す。人の経脈走行は同じではなく、絡脈は人により違うところから分かれる。」とあり、人により、経脈や絡脈は異なる走行をしていることが、述べられ、(絡穴は、)望診で分からないときは、触診で探す必要があることが記述され、腧穴(ツボ)の部位を決めるのに、「触診」が重要であることが示されている(文献6)。
このように、「触診」は、「診察・診断」の次の段階の「治療」の際に、刺鍼・施灸する部位を確定する「取穴」のためにも必要な技術である。
(3)刺激量の確定
刺激量は、臨床経験を積んでいけば、「1)刺激部位の確定」と「2)刺激対象の確定」の過程で、刺鍼方法(単刺、雀啄、置鍼、パルス刺激、など)を考慮しながら、ある程度、決めることができるようになる。
しかし、身体には個性があるし、病気の状態・程度によっても異なるので、臨床経験を積んでも、刺激量は、治療開始前に確定するのが難しいこともある。
そこで、より確実な方法は、「触診」で、刺鍼刺激や施灸刺激を与えることで生じる生体の変化を、適宜、確認しながら、反応が目的の変化を起こす時点まで刺激し、そこで刺激を終了することである。
このことは、同時に、患者の感受性を判断する事とも関係する。治療前の診察や治療前の「触診」により、患者の感受性がある程度予測されるが、実際の刺激にどの様に感応して、体表の所見がどの程度変化するかを確認することも、刺激量を決めることに繋がる。
このように、刺激前の「触診」や、刺激途中での「触診」で、所見の変化を確認することにより、適切な刺激量、刺激時間を決めることができ、治療の効果をより適切にあげることができるようになる。
(4)治療後の変化の確認
さて、治療が進み、鍼灸刺激(治療)を終えた後には、その治療効果を確認する事になる。一般的には、軽くなったかどうかを患者に訊ねて確認することが多いと思うが、所見が、刺激前の状態から治療後にどれくらい変化・改善したかを「触診」で確認することも重要である。治療前後の変化を確認することで、患者の鍼灸刺激による改善の度合いが分かり、治療刺激に反応する感受性も加味することで、治療後に残る所見を取り除くのに、その後、どれ位の治療期間や回数が必要であるかの見通しを立てる判断材料を得ることにもなる。
鍼灸の科学的な研究を行う立場の研究者からは、鍼灸治療は患者の症状の訴え(主観)に頼り、客観性に欠けると言われるが、治療者の主観とは言え、所見の変化を確認することにより所見の改善を確認することは、鍼灸臨床では重要なことである。
3.触診の意味、意義
以上述べてきた様に、鍼灸治療においては、「触診」は、診察、診断に重要であるのみならず、治療部位を確定し、治療用具を選び、鍼の深さや単刺・雀啄・置鍼などの刺激方法を決め、刺激量を確定し、治療の終了時点を決め、そして、治療後の変化を確認するという、鍼灸治療の全行程おいて必要な技術であり、治療の継続期間や治療回数の予測にも繋げることが出来るものである。
このように、「触診」は、鍼灸治療の上では、最も基本となり、基礎となる方法であることがお分かりいただけたと思う。(第2回へ続く)
<引用文献>
(1)“WHO STANDARD ACUPUNCTURE POINT LOCATIONS IN THE WESTERN PACIFIC REGION”, WHO Western Pacific Region Office, Manila, Philipines, 2008年.
(2)柳谷素霊、「手に触れる経絡」、『東亜医学』1939年、第7号.
(3)岡田明祐、『経絡治療と鍼妙』1997年、74頁、たにぐち書店、東京.
(4)藤本蓮風、『体表観察学 日本鍼灸の叡智』2012年、212頁、緑書房.
(5)入江靖二、『図説 深谷灸法―臨床の真髄と新技術―』昭和55年、6-7頁、自然社.
(6)南京中医学院篇、『黄帝内経霊枢』経脈 第十、1999年、257-258頁、東洋学術出版、千葉.
執筆
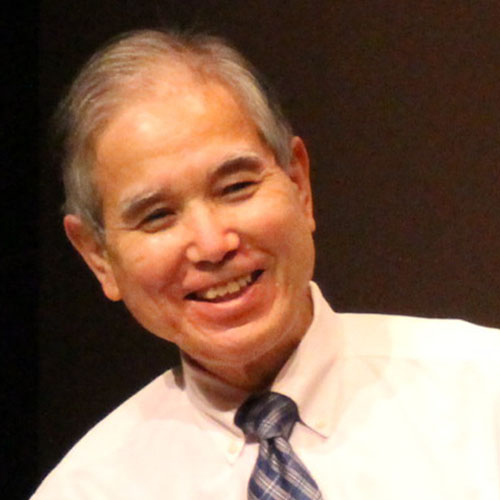
形井 秀一(かたい・しゅういち)
洞峰パーク鍼灸院院長
つくば国際鍼灸研究所所長
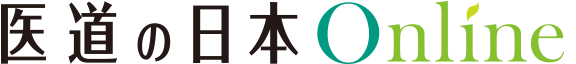
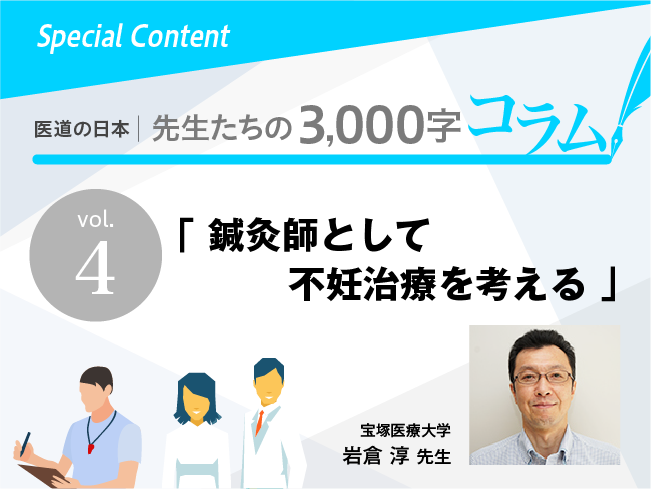

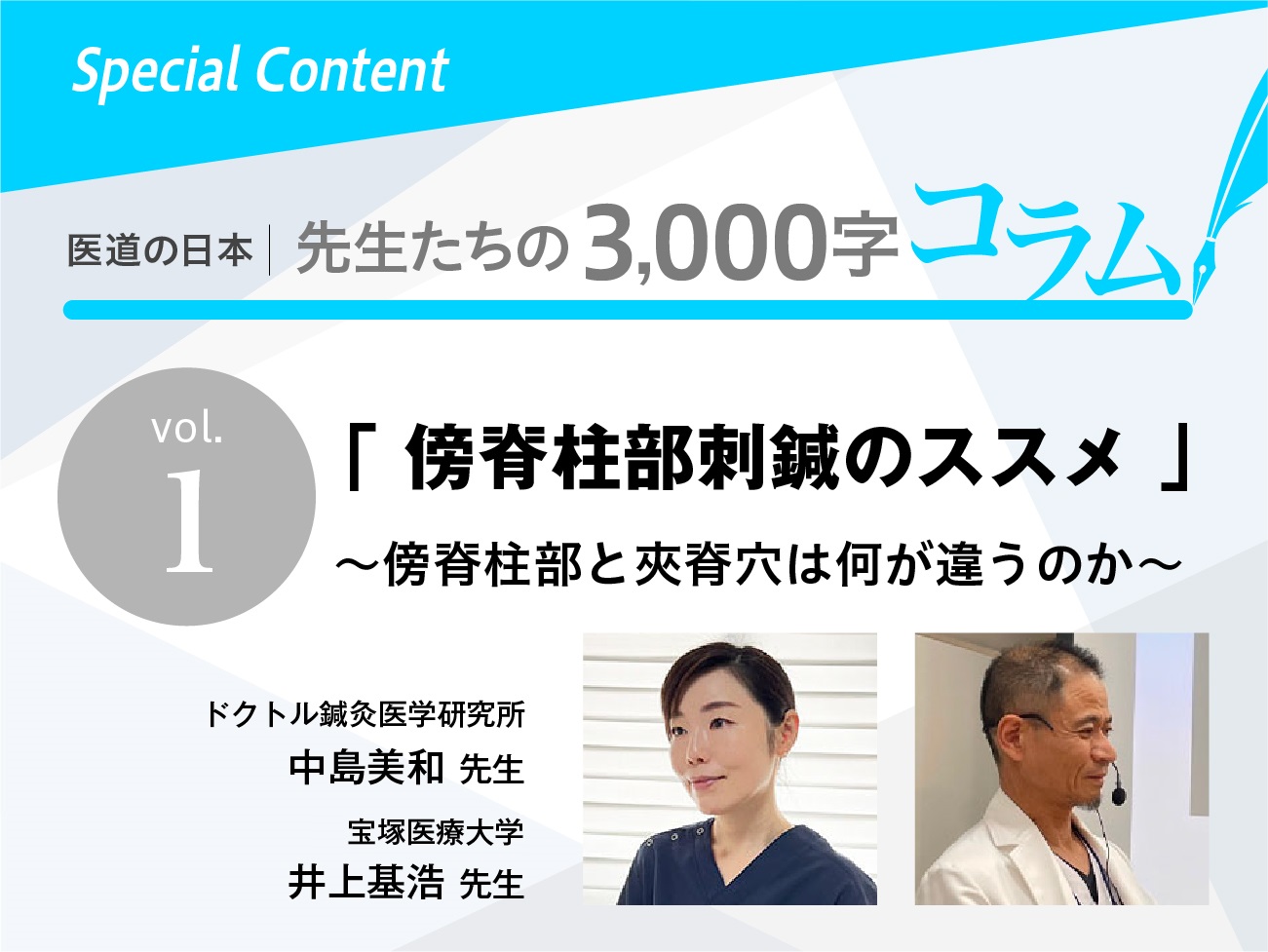
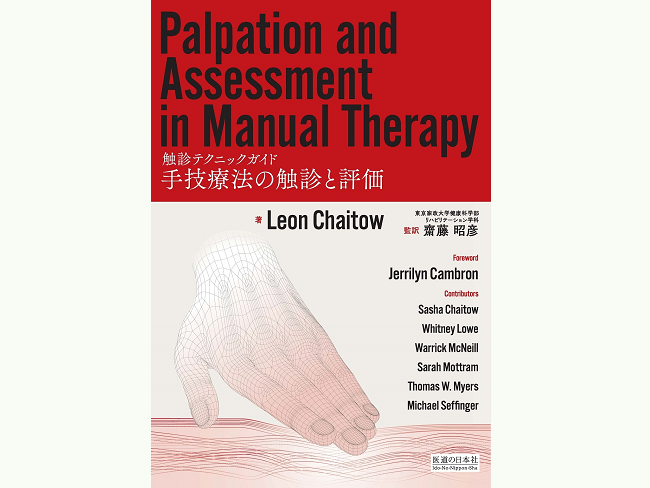
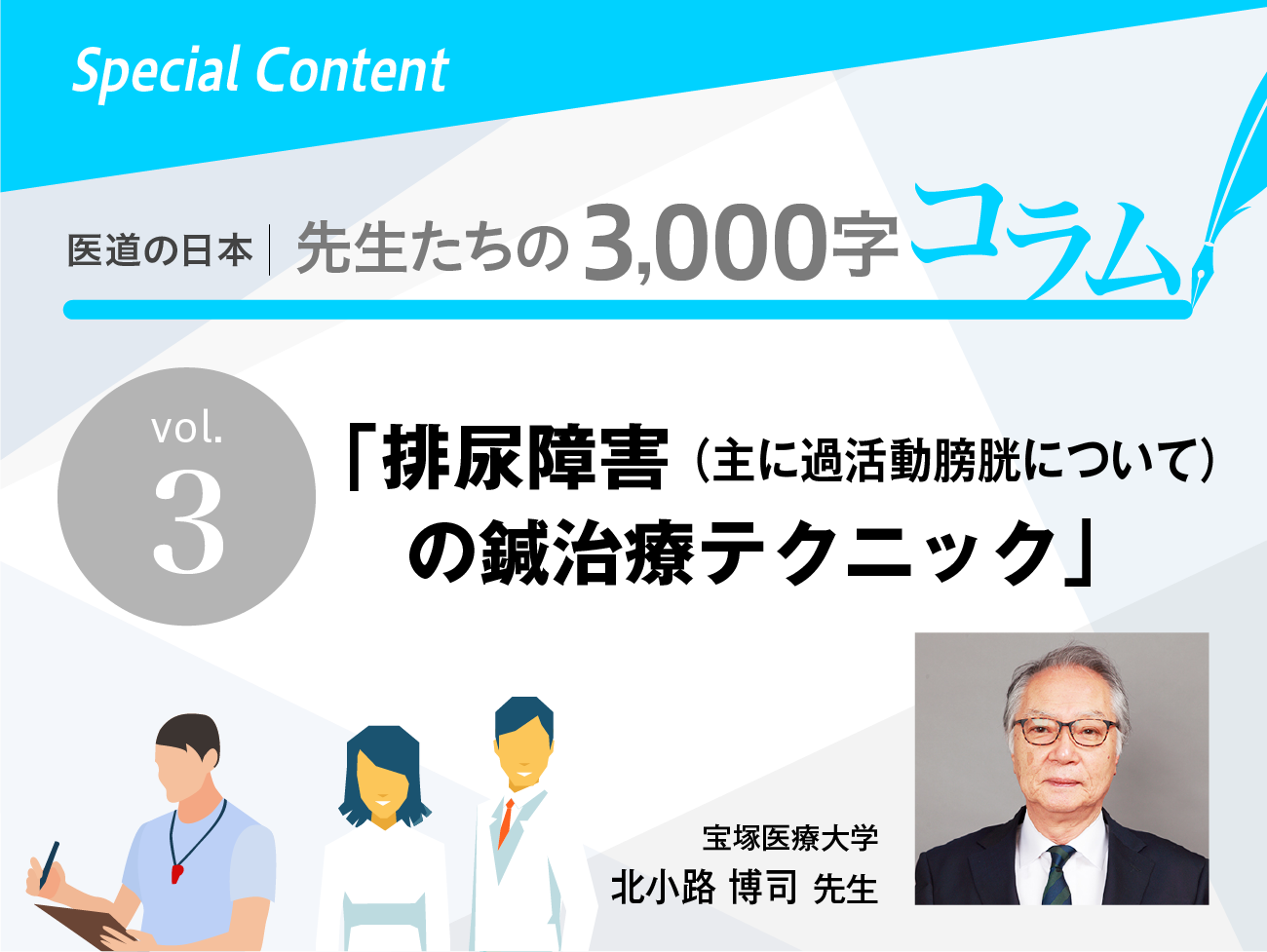
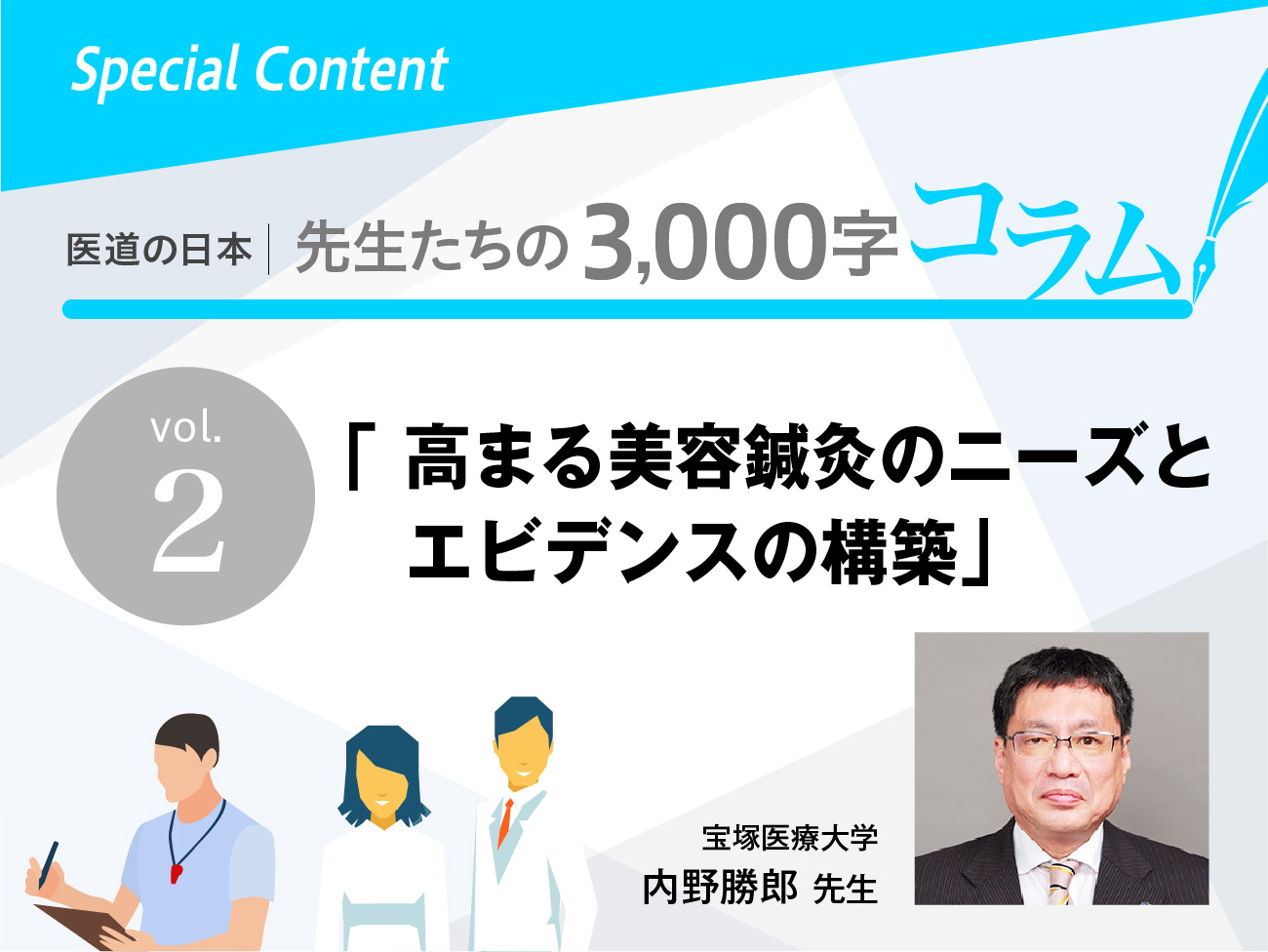
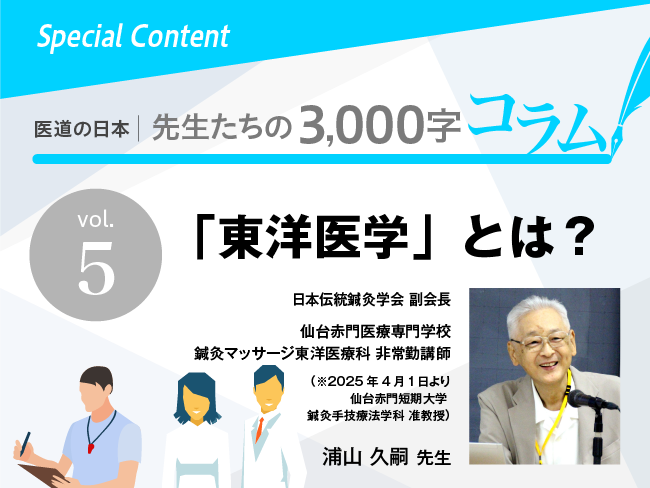
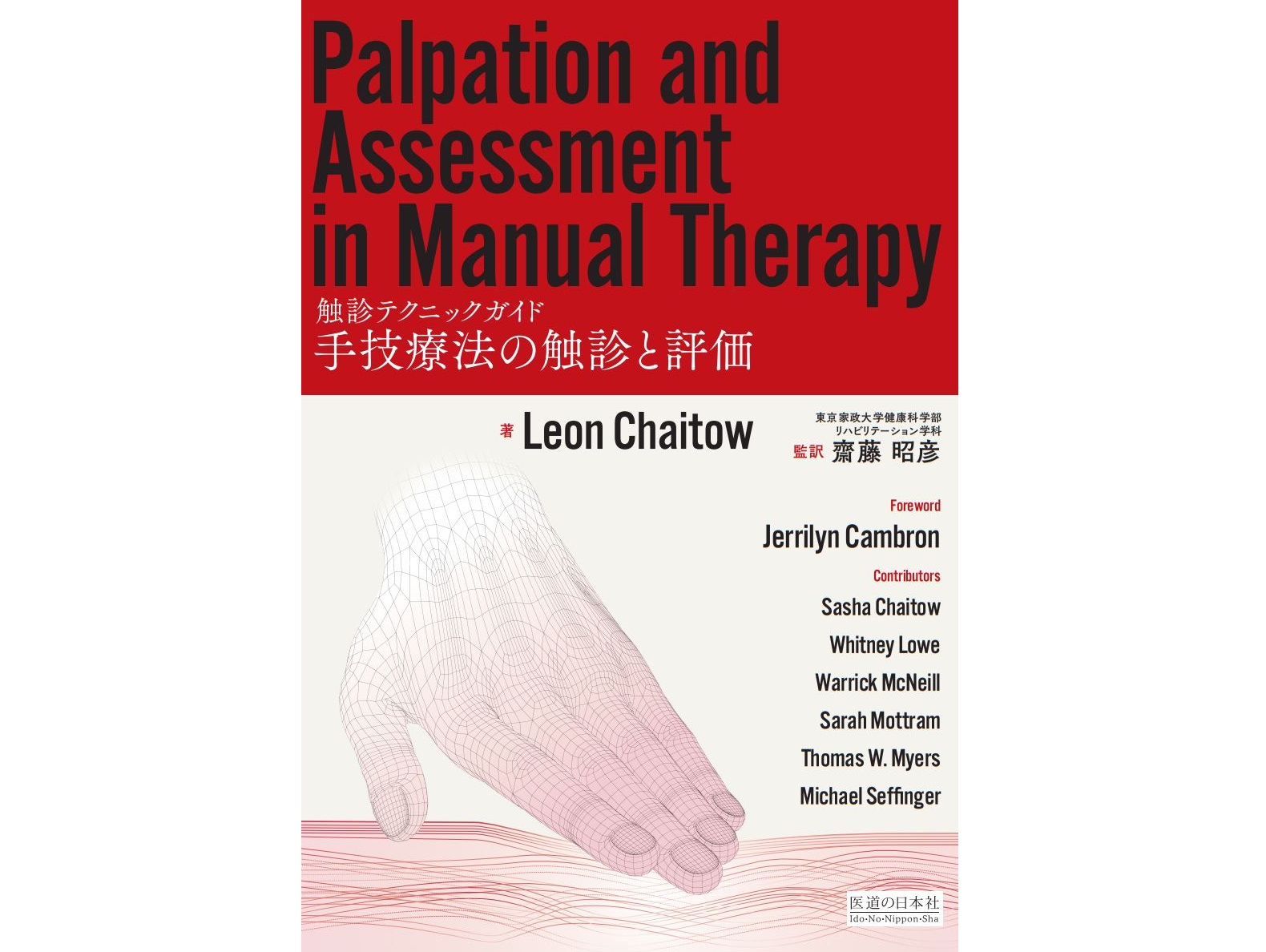






















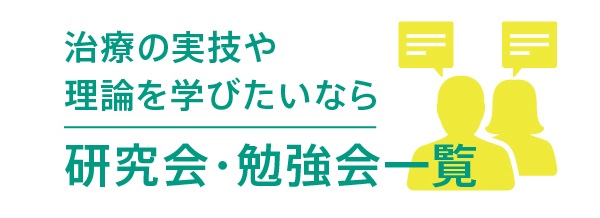
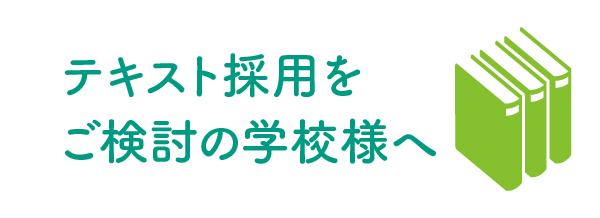
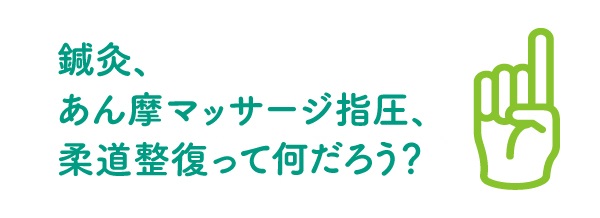
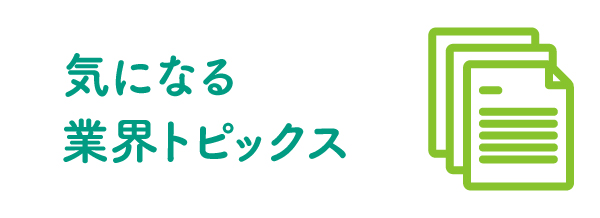




![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)